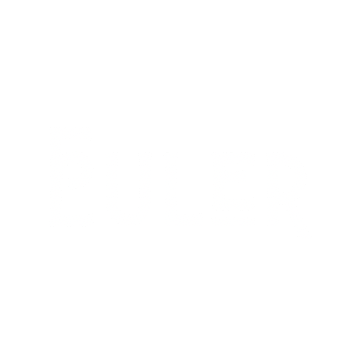スペイン北西部、サンティアゴ大聖堂へと続く巡礼の道。
信仰の有無を問わず、世界中から人々が集まり、それぞれの理由を胸にただ歩き続ける。
多くは宗教的な意味を求めて。あるいは人生の転機に差しかかり、何かを見つけたいと願って。
理由は人の数だけあるが、やることは同じ、歩く。ただそれだけだった。
僕もその道に足を踏み入れた。
けれど歩き出す前夜、ポルトガルの安宿で寝袋にくるまりながら、ほとんど眠れなかった。
「本当に300キロを超える道を歩き切れるのか」
その問いが胸に居座り、目を閉じても、不安が体の奥からじわじわと込み上げてきた。
翌朝、背中に荷物を背負い、一歩を踏み出す。
街を抜け、田畑を越え、黄色い矢印を追いながら歩いていると、「思ったよりいけるかもしれない」と思った。
しかしその自信は、数日も経たないうちに簡単に崩れた。
背中の痛み、足のマメ、容赦ない日差し。
「これが毎日続くのか」と考えるだけで、心が押しつぶされそうになった。
静かな道しるべ

孤独に歩く時間は、ただの沈黙ではなかった。
長い一本道で誰とも言葉を交わさない時間、ふと独り言をつぶやいている自分に気づいた。
最初は気を紛らわせるためのものだったが、次第に「もう少し頑張れ」「大丈夫だ」と、自分を励ます声に変わっていった。
まるで自分の中に新しい友達が生まれたようで、その声に救われながら歩いていた。
孤独に耐えるのではなく、自分と仲良くなる時間に変わっていった。
そして歩くほどに、普段なら思い出すことのない記憶が次々に浮かんできた。
家族とのささいな会話、友人と笑い合った場面、イギリスで居候していた友人宅での食卓の風景。
当たり前すぎて意識もしていなかった断片が、歩くことでひとつずつ掘り起こされていく。
それは懐かしさというより、自分の内側から呼び出される支えだった。
その一場面ごとに「ありがとう」と言いたくなった。
そして実際に声に出したとき、胸の奥で何かがほどけた。
幸せは遠いゴールの先にあるんじゃない。
感謝が自然にあふれた、その瞬間こそがすでに幸せだったのだ。
「ありがとう」と思えるのは、すでに満たされている証だ。
不足しているとき、人は感謝を忘れる。
でも心から「ありがとう」とこぼれたなら、それは今あるものに気づいているということ。
つまりその時点で、もう幸せの中にいるのだ。
見覚えのない、懐かしい場所

ポンテ・デ・リマへ続く道

道のりはやっぱり厳しかった。
小さな村を抜けても店ひとつなく、空腹のまま次の町まで歩き続けるしかない日もあった。
腹が減ると頭の中は食べ物のことばかりになる。けれど途中で座り込んだところで、状況は何も変わらない。
「仕方ない、受け入れるしかない」
そう自分に言い聞かせるしかなかった。
その感覚は、空腹そのものよりも、「自分をどう納得させるか」という戦いに近かった。
大雨に打たれて体が冷えきり、ついに足が止まったこともある。
そのとき、道沿いの古い家から老人が声をかけてくれた。
屋根の下に入れてもらい、水を分けてもらっただけなのに、胸の奥が一気に緩んだ。
「見知らぬ誰かの善意に、こんなにも救われるのか」
そう思った瞬間、張りつめていた心がほどけて、涙が出そうになった。
歩いていると、通り過ぎる車がわざわざクラクションを鳴らし、手を振ってくれることもあった。
ほんの数秒の合図。
それでも見てくれている人がいるという事実が、背中を押してくれた。
孤独の中で、そうした小さな出来事が何度も自分を歩かせてくれた。
孤独も、空腹も、雨の冷たさも、人の優しさも。
それはただの出来事ではなく、「お前はどう受け止めるんだ」と問いかける試練だった。
同じ体験でも、受け止め方次第で意味はまるで違う。
苦しみの中にしか見えないものもあれば、優しさの中でしか感じられないものもある。
結局は自分の心のあり方が、すべてを決めていた。
歩き続けるうちに、僕は赤ん坊のようになりたいと思うようになった。
泣きたいときに泣き、嬉しいときに笑い、眠いときに眠る。
ただ目の前の世界をそのまま受け入れる存在に。
大人になるほど、比較や理屈が先に立ち、素直に受け取ることが難しくなる。
でも歩くごとに、それらが剥がれ落ちていくのを感じた。
心が軽くなるのは、何かを得たからではない。
むしろ余計なものを手放せたからだった。
道の途中で目にした夕暮れや、ふとした笑顔、何でもない瞬間。
それらはどれも特別ではなかったけれど、心が空っぽに近づくほどに新鮮に映った。
「生きるとはこういうことかもしれない」
そう思えるほど、景色や出来事がまっすぐに胸に届いた。
– Camino Portugués –
ポルトガルからサンティアゴへの道

カミーノは決して思い通りには進まなかった。
予定は崩れ、予測は外れる。
けれど、その不確かさこそが道の本質だった。
出来事を支配しようとするのではなく、受け止め方を整えること。
それだけが僕を前へ進ませてくれた。
振り返れば、この道は旅であると同時に心の巡礼だった。
300キロを超える道のりは、外の景色を進む道であると同時に、自分の内側を深く掘り下げる道でもあった。
孤独を通して自分自身と友達になり、苦しみの中で感謝に気づき、余計なものを手放すことで心は軽くなった。
最後に辿り着いた答えは驚くほどシンプルだった。
幸せは「ありがとう」がこぼれたその瞬間にある。
感謝が溢れるとき、人はすでに満たされている。
その気づきを抱きながら歩いた道は、始まりから終わりまで、ずっと幸せの中にあったのだ。
サンティアゴ・デ・コンポステーラ