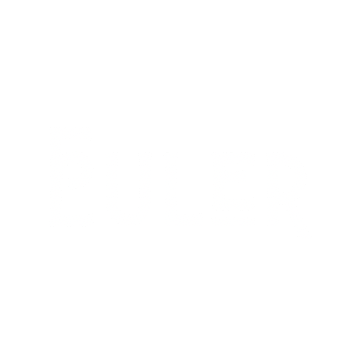現地の友人の勧めに従い、京都市内から北へ車を走らせることおよそ二時間半。
若狭湾の静かな入り江に、伊根の舟屋は並んでいた。
海面すれすれに木造の家々が立ち並ぶ光景は、まるで時間の流れから切り離されたようで、初めて目にする者を一瞬で魅了する。
観光地としてすっかり有名になった今でも、その湾に映る影はどこか懐かしく、心を静かに揺らす。
伊根の舟屋

けれど、舟屋はもともと観光のために建てられたわけではない。
江戸時代から昭和にかけて、漁師たちの生活の場であり、仕事の拠点でもあった。
舟を収めるための一階と、住居や作業場として使われる二階。
その構造は、漁と共に生きる人々の暮らしそのものだったという。
きっと朝には舟を出す音が港に広がり、夕方には網を干す姿や漁具を直す手が並んでいたのだろう。
桟橋から子どもたちが飛び込む水しぶきと笑い声も、この風景には欠かせなかったに違いない。
僕はその情景を想像するたびに、現代の伊根との落差を感じる。
今の舟屋は保存や観光のために整えられ、美しい景観として多くの人を惹きつける。
確かにそれは町の経済を支え、未来に繋げる力でもある。
けれど、どこか「展示品」のように静まり返った舟屋を前にすると、本来そこにあった生活のざわめきが聞こえてこないことに寂しさを覚える。
水に寄り添う家々

町の人々も複雑な思いを抱えているだろう。
観光客が増えたことで町が潤う一方、かつての生活のリズムは大きく変わったはずだ。
観光客の視線にさらされることを負担に感じる人もいるかもしれない。
しかし同時に、舟屋が注目されることで伊根という小さな町が存続しているのも事実だ。
経済と暮らし、誇りと戸惑い。そのはざまで揺れながら、この町は今も生きている。
舟とひと息

釣り糸より長い沈黙

舟屋に腰かける午後

僕は歩きながら、何度も「もし昔の伊根を見られたら」と思った。
舟屋がただの「観光資源」ではなく、生活そのものとして息づいていた頃の姿を。
もちろん、それは叶わない願いだ。
過去はもう戻らないし、今ここにある舟屋もまた、未来に向けて変化していく。
それでも僕は、この「失われた時間」を想像することで、伊根をより身近に感じるのだと思う。
目に見える景観だけでなく、そこに生きた人々の暮らしを思い描くように。
商店前の日常

観光地として生き続ける町は世界中にある。
けれどその美しさを味わう一方で、自分自身も観光客としてその場に足を踏み入れていることに葛藤を覚える。
町を支える経済と、そこにあった暮らしのリズム。
その両方を大切にする方法を、訪れる僕たち一人ひとりが考え、共に探していく必要があるのだろう。
僕はこれからも旅をし、いろんな町を訪れるだろう。
そのたびにきっと、同じ問いを抱くに違いない。
「今ある姿の前に、どんな時間が流れていたのか」と。
伊根の舟屋は、その問いを僕の中に強く刻んでくれた。
水面に寄り添うもの