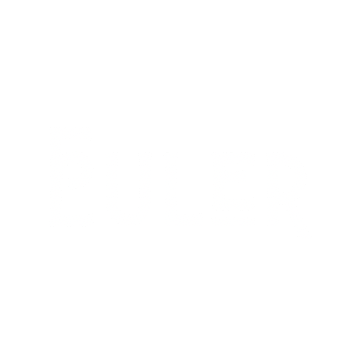オーストラリア東海岸に浮かぶノース・ストラドブローク島。
地元の人は「ストラディー」と呼ぶ。
ブリスベンからフェリーで1時間、アクセスは驚くほど簡単なのに、着いた瞬間から別世界になる。舗装された道路の先には小さな集落が点在し、街のざわめきは完全に消えていた。
海は、暮らしの一部のようにそこにあった。
観光客がいないビーチはすぐに見つかる。波打ち際に腰を下ろすだけで、周りには誰もいない。透明度を語るより、誰もいない砂浜で足を沈めるだけで十分だった。
海は語らない、ただ黙って耳を貸してくれる。
大地と海の対話

秘密の水たまり

島の真ん中にあるブラウンレイク。
初めて見たときは、その紅茶のような色に驚かされた。
けれど足を入れると水は驚くほど澄んでいて、指先や足元の砂まではっきり見える。
色の理由は、周囲のユーカリやティーツリーから溶け出した成分だという。
知ればより、この色が湖の個性のように思えてくる。
岸辺では子どもたちが笑いながら飛び込み、茶色い水面に波紋を広げていた。
その姿は、まるで紅茶のカップの中で遊んでいるようで、眺めているだけで心がやわらいだ。
忘れられた布、生きる水

擬似 Tea Bag

水面ティータイム

夕方の島は一気に表情を変える。
崖の上にシートを敷き、お気に入りのビールを片手にただ海を眺める。
太陽は空を紫とオレンジに変えながら沈んでいく。
毎日同じように訪れるはずの夕日なのに、見飽きることはなかった。
どんなに笑い声が響いていても、太陽が沈む瞬間には、みんな言葉を忘れて空に見入っていた。
光を抱く木

夜になると島は裏の顔を見せる。
ある日はブッシュの奥、4WDのライトを頼りに森を抜けると、そこにはDJブースと焚き火。スピーカーからあふれる音と星空が混ざり合い、ローカルもバックパッカーも肩を並べて踊っていた。音楽フェスでもクラブでもない。
島の人間が、その夜を「そうしたいからそうしている」だけの集まりだった。
また別の日には、白い砂浜に即席のテントクラブが立ち上がる。
カラフルな照明に照らされて、波の音がBGMに混ざる。移住者も旅人も、出どころはバラバラなのに、気づけば同じリズムで揺れていた。
踊り疲れてテントの外に出ると、波打ち際の暗さがやけに優しかった。
地図にないドライブ

森の奥のダンスフロア

海が見守る夜の舞台

砂浜ダンスフロア

暮らしの中にある小さな出来事も、島を特別にしていた。
レストランで働く友人が持ってくるのは、工場で廃棄されるはずだったラベルなしの缶ビール。ブランドも説明もない、ただの缶。
でもそれを片手に夜を過ごせば、不思議と十分だった。
焚き火の明かりと潮風、缶のプルタブを開ける音。それだけで、島の夜は完成していた。
無名のビールで酔いが回る頃、森からコアラの鳴き声がした。
暗闇を進むと、そこにいたのは木の上じゃなく、足元をのっそり歩くコアラだった。
夜な夜なそんな出会いを楽しむのも、オーストラリアらしい夜の一部だった。
移動はヒッチハイクが基本で、予定を立てなくても不思議とどこへでも行けた。
便利さじゃなく、ゆるやかな繋がりで生活が回っていた。
名もなきヒーロー

Straddie Road

ある日、海を撮ろうとカメラを構えた。
ふと横を見ると、真正面にカンガルーがいた。
僕も驚いたが、向こうも同じ顔をして驚いていた。
静かな海辺で、互いに同じリアクションをしていることに、ひとり笑いが込み上げた。
夕陽の番人

気づけば数ヶ月もいたが、ノース・ストラドブローク島は「観光地」なんて言葉で片づけられない。
ここでは景色と時間と人が自然に混ざり合い、滞在しているうちに日常まで島に飲み込まれていく。訪れる人の中には、そのまま移り住んでしまう者も少なくないそうだ。
島の引力に抗える人間なんて、きっと多くはないだろう。
Straddie Sunrise