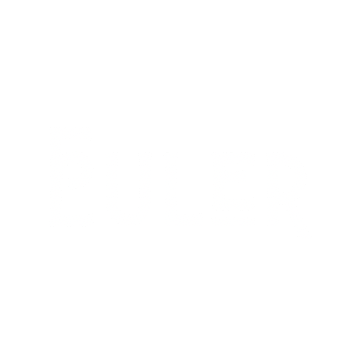海外にいても日本にいても、初対面の人と話すと、決まって聞かれることがある。
「君は、どこのハーフなの?」
その問いに、僕はいつも深く考えず「イランとのハーフだよ」と答えてきた。
それは紛れもない事実だし、僕の体の半分には確かにペルシャの血が流れている。
けれど、その言葉を口にするたび、正しいはずなのに、喉の奥に小さな違和感が残った。
嘘をついているわけじゃない。でも、胸の奥で何かが引っかかる。
自分を形づくっているはずの、もうひとつの場所。
その「イラン」という国について、僕は一体何を語れるだろう。
美味しい料理のことか。親戚の断片的な記憶か。
正直に言えば、どれも曖昧だった。ニュースの断片、危険そうな国、遠い国。
そんな輪郭の粗い、誰かが作ったイメージしか僕は持っていなかった。
自分の半分を占める場所のことを、実は何一つ知らない。
その事実に気づいたとき、自分がひどく薄っぺらで、どこにも根を下ろしていない存在のように思えた。
それから、少しずつ向き合うようになった。
去年から本を読み漁り、現地のニュースを追い、そして何より父とイランについて議論する時間が増えた。
父の記憶に残るかつての美しい風景と、今のイランが直面している容赦のない現実。
その間に横たわる果てしない距離を、言葉で埋めるように僕たちは話した。
調べれば調べるほど、イランは画面越しに見てきた姿とはまるで違う顔を見せてくれた。
歴史は気が遠くなるほど分厚く、過去のものとして切り離されていない。
そして何より、人が驚くほど近い。親切で、よく笑い、よく話す。
初対面の相手でも、気づけば家族のように食卓を囲んでいるような、不思議な温度がある国。
「危険な国」というイメージの裏側には、拍子抜けするほど穏やかで、誇り高い日常を生きる人たちの姿があった。
けれど同時に、今この瞬間も、イランの街頭では魂を削るような出来事が起きている。
自分たちの自由を手放さないために、命を賭けて立ち続ける人たちがいる。
今日、家を出たらもう二度と戻れないかもしれない。
それでも、拳を突き上げるという選択。
その覚悟の重さを想像して、何度も胸が詰まった。
僕は今の動きを心の底から応援したい気持ちと、どこかで踏みとどまってしまう感覚を、同時に抱えている。
応援したい。
でも、無条件で肯定することに、少しだけ後ろめたさが残る。
今の国民の結束を見ていると、王を追い出した革命前の高揚と、不意に重なって見えることがある。
当時も、人々は「これで変われる」と信じていた。
けれど、時間が経って振り返ったとき、その選択が本当に正しかったのか、いまだに答えは一つではない。
そもそも経済制裁がなくなれば、何かは変わるのだろう。ただ、その変化が本当に人々の暮らしに届くものなのか、僕にはどうしても疑いが残る。
政治の大きなチェス盤の上で、イランはいつも誰かの都合で動かされているように見える。
自由を求める叫びさえも、どこか遠い国々の政治的な道具にされているような気がして、素直に頷けない自分がいる。
平和な場所から「自由のために戦え」なんて無責任に叫ぶことは、僕にはできない。
そんな綺麗事では片付けられないほど、あの国の現実は複雑で、泥臭く、そして痛切だ。
それでも、僕がイランに惹かれている理由は、何か政治的なメッセージを発信したいからじゃない。もっと静かで、自分勝手な理由だ。
自分の中に流れている半分を、文字や知識ではなく、体温として感じてみたい。
頭で理解するのではなく、心臓の鼓動で納得したい。
経済制裁がどうとか、デモの正義がどうとか、そんな理屈のレイヤーを一枚剥いだところにある、剥き出しの日常に触れたい。
だから今年、僕はイランを目指そうと思っている。
本来は1月中に渡航する予定だった。
けれど、カナダに住むイラン人の叔母から連絡があり、
「4月にイランへ帰るから、そこで会おう」と言ってくれた。
日本の春分の日にあたる頃、イランでは新年を迎える。
その節目に合わせることにして、僕は了承した。
もし、数日前からイランに入っていたら、今の情勢をどう受け止めていたのか、想像もつかない。
だから今は、焦らず、準備に徹することにした。
簡単な旅になるとは思っていない。無事に入国できるのかもわからない。
途中で扉が閉まってしまうかもしれないし、計画通りに進まない可能性のほうがずっと高いだろう。
それでも、あの国を、想像の中だけに置いたままにしたくなかった。
家族に会いに行くっていうのも、自分に言い聞かせている理由のひとつだ。
けれど一番は、イランを遠いニュースとしてではなく、僕が今生きているこの生活の延長線上に引き寄せたいと思ったから。
スマホの画面越しでもなく、父の記憶の残り香でもない。
今のイランの風を吸い、土を踏み、そこに生きる人たちと同じ目線で空を見上げてみたい。彼らの抱える怒りも、悲しみも、そしてその奥にある美しさも、自分の距離で感じてみたい。
行けるかどうかは、正直わからない。
運が悪ければ、空港のロビーで引き返すことになるかもしれない。
それでも準備を始めたのは、いつかまたどこかの街で、自分のルーツを聞かれたとき、今度は少し違う顔で答えられる気がしたから。
「イランだよ」
そう言って、その言葉を、ためらわずに相手に差し出したい。
この文章も、結論じゃない。ただ、知ろうとし続けた時間の途中にある、未完成な記録だ。
それでも、イランについて考え始めたことで、もう何も知らなかった頃の僕には戻れなくなった。
それだけで、今は十分だと思っている。